
上場企業やその子会社、また、上場準備会社などは、監査法人などの法定監査を受けているケースが多く、厳格な会計基準に基づき財務諸表を作成しなければなりません。従いまして、会計処理に関し企業会計基準と税務基準のギャップが大きくなり、税務申告調整項目が多岐にわたり、税務申告は複雑になります。
上場企業などの財務諸表作成に特徴のある企業会計基準は、以下のとおりです。
1.税効果会計
税効果会計とは、企業会計基準で計算された「収益」及び「費用」と法人税法で計算された「益金」と「損金」の期間帰属のズレを、「法人税等」の前払費用処理または未払費用処理によって、損益科目である「法人税等」を期間配分することにより、税引後当期純利益の期間比較を可能にすることを目的とした会計処理の方法です。
税効果会計に従い会計処理しますと、「繰延税金資産」や「繰延税金負債」が計上され、法人税での申告調整が必要となります。
2.減損会計
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性に着目し、固定資産の使用状況の変化、経営環境の悪化などを原因として、その固定資産が投下資本を回収できなくなった場合に、その回収可能額まで評価を引き下げる会計処理を言います。
固定資産について、減損会計を適用し、減損損失を計上したとしても、法人税法上は、ほとんどの場合、損金として認められません。従いまして、申告調整が必要です。また、建物を減損した場合、税務上の減価償却との調整で毎期、別表での減算処理が必要となります。
3.金融商品会計
有価証券などの金融商品の評価基準は、従来は、「取得原価主義」によるものでした。しかし、金融市場の発達により、金融派生商品(デリバティブ)など、いろいろな金融商品が開発され取引されるようになると、取得原価によるバランスシート計上では、マーケットリスクを会社の財政状態に的確に反映することが難しくなってきました。
金融商品会計基準の基本的な考え方は、「時価評価」によるオンバランスです。
また、金融商品会計基準が取り扱っている取引は、一般に金融商品と呼ばれている株式、国債、社債などの「有価証券」だけでなく、貸付金、借入金などの「金銭債権債務」、金利スワップ取引、通貨オプション取引などの「デリバティブ取引」、さらには、ゴルフ会員権なども含まれ、その適用は広範囲に及びます。
金融商品はその仕組みが複雑なものもあり、正確な理解のうえで会計処理を行い財務諸表に計上しなければなりません。また、有価証券の評価損の計上基準などは、法人税法の規定と異なっているものもあり、申告調整が必要となる場合があります。
4.退職給付会計
退職給付会計は、従業員の退職金制度に関する会計基準です。
退職金制度には、従業員の将来の退職時に要する給付に備えて、企業内部で資金を蓄積していく「退職一時金制度」と信託銀行など企業外部に資金を拠出し運用していく「企業年金制度」の大きく2つに分類されます。
退職給付会計では、企業が採用する退職金制度の種類にかかわらず、保険数理計算に基づき、退職給付債務(PBO)を算定し、それをバランスシートに反映させる会計手法です。
現在では、法人税法上、「退職給与引当金」の計上は認められておらず、従って、会計基準で「退職給付引当金」を計上している場合には、申告調整が必要となります。
5.その他
上記以外にも、現在、日本の会計基準とIFRS(国際財務報告基準)のコンバージェンスが進められています。
当事務所では、上記のような複雑な会計基準への対応とそれに基づく税務申告にも対応します。 
さらに、上場企業の子会社や上場準備会社では、申告調整以外にも監査法人からの指摘にどう対応してよいか、決算をどう締めればよいか、会計業務に困っている企業もたくさんあります。
当事務所は、大手監査法人に勤務していた実績をベースに、公認会計士事務所として、税務以外の会計・財務の良きアドバイザーとして活動しています。
※ 有価証券報告書などディスクロージャー書類の作成代行は、当事務所が提携している監査法人又は会計事務所で行います。



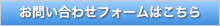






 会社全般サービス
会社全般サービス
